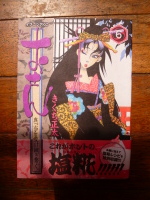ほし太の日向ぼっこ
漫画「おせん 真っ当を受け継ぎ繋ぐ」 きくち正太 作
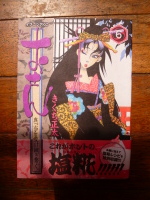
娘が好きでずっと買っている漫画の最新刊。
今回のテーマは『塩糀』でした。
今の塩糀ブームを作ったのも実はこの「おせん」。
それから国民的なブームになったものの、
この本によると、
本当の塩糀は別物でした。
だいたい知られている塩糀のレシピは、
糀3に対して塩1。
たとえば糀が1キロなら塩が300g、水1キロを混ぜて、
毎日かき混ぜて、一週間発酵させたら後は冷蔵庫で保存。
というもの。
でもこの本によると、
糀が三升に塩一升という、同じ3対1でも重量でなく量なんだとか。
それもしっかり発酵させたら冷蔵保管ではなく、
常温で何年でも大丈夫ということ。
特に茄子を丸ごと1本この塩糀に漬けると、
皮はプリプリで実はジューシーらしい。
今度はこの塩糀を作ってみたいです。
追伸
昨日8月の「毎月お届け干し芋」出荷しました。今月のお宝ほしいもは、“安納芋四切りほしいも”です。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
毎月お届けの「今月のお宝ほしいも」の直接ページはこちら
今月のお宝ほしいも
【ほし太の日向ぼっこ】
安納干し芋の四つ切り

定期宅配干し芋セットの今月のおまけ干し芋は、
「安納芋の四つ切り」でした。
会員さんへのパンフレット用に撮影しましたが、
毎日干し芋を扱っている私達スタッフにとっても、
これはかなりレアな干し芋です。
一年に一度、
こういう機会でもない限りめったにお目にかかることはありません。
ましてや食べることはないので、
本当に見るだけなんです。
このおまけの干し芋になるのは、
こだわった農家さんが、
ごくわずか作った、珍しい干し芋ばかりなので仕方がないのですが、
「宝物のような干し芋」という意味で、
「お宝干し芋」と名づけました。
それが、
楽天市場店だけの限定販売で毎月10セットだけ、
お宝干し芋だけのセットが販売されることになりました。
私ももしかしたら買ってしまうかもしれません。
もし見かけたら要チェックですよ♪
【ほし太の日向ぼっこ】
かぼちゃの豊作

父が、借りている畑で作ったかぼちゃ、
今年は豊作みたい!!
今日はこれだけ収穫してきて、
畑には、まだまだ沢山あるというので、とっても楽しみなんです♪
特に白いかぼちゃは、勝手に生えて勝手に実になったそう。
いつも台所で出る生ゴミを、
畑に持っていってたい肥にしてもらうのだけど、
その中に入っていた種から立派に生長しました。
カボチャや冬瓜はこういうことって結構あります。
たかおさんのスイカもそうだけど、
夏のツル性の野菜はなかなかエコです。
【ほし太の日向ぼっこ】
噂のスイカ

干し芋農家のたかおさんの庭先で、
スイカのツルを見ました。
毎年庭に生えてくるのだそう。
庭先で食べたスイカの種が自然に芽を出すのでしょう。
確かに毎年この庭で
たかおさんが作った美味しいスイカをご馳走になります。
畑に生えたスイカと同じように
大事に見守られている様子がよくわかります。
そんな優しい人だから、
たかおさんが作る干し芋も野菜も果物も、
みんな美味しいのでしょうね♪
【ほし太の日向ぼっこ】
フィットネスシューズ

生活クラブの提携メーカーのひとつ、
「パラマウント・ワーカーズ・コープ」の展示販売会に行ってきました。
まずは足の話を聞きました。
足には28もの骨があって、
それは実に身体の4分の1の骨にあたるのだとか。
かかとに重心を置き、
左右の親指を蹴って歩くのが自然なのだけれど、
それが出来ていないために足やひざの変形がおこり、
腰や膝痛など、からだの不調も起きるのだそう。
足の形は人それぞれなのに、
既製の靴にはそんなにバリエーションがなくて、
自然、靴に足を合わせるということに…。
ここの靴は完全国産の手作りで、
1人1人の足を測定し全体のバランスをはかり、
その人にピッタリの靴を選んでくれます。
だから、予約制で一人ひとりしっかりと時間をとってくれます。
色々話を聞くうちに、
私も「フォーマル用の靴を買いたい!!」と思ったけど、
私の足にピッタリのサイズのものは今は無いそうで、
木型はできているので、もうすぐ販売されるというのです。
足に合わないものはけして勧めないという姿勢が嬉しかったです。
結局フィットネス用のスニーカーを買うことにしました。
このニューバランス製の靴は、
日本で代理店契約しているのだそう。
私のサイズにあうものをセレクトしてもらい、
その中から気に入ったものを選びました。

もう一つすごいと思ったのは、
その場で足にあったインソールを作ってくれること。
それは、仏シダス社製のオーダーメイドインソールで、
もちろん私も作ってもらいました。
スニーカーとインソールで2万円ちょっと、
自分の足にピッタリのオーダーでこの価格は、
ちょっと驚きの安さです。
早速月曜日のエアロビでおろすのが楽しみ~♪
【ほし太の日向ぼっこ】
黄な粉ヨーグルト

豆乳で作ったヨーグルトに、
さっそく「黄な粉」をかけて食べてみました。
ちょうどお盆に義母が作ってくれた、
「おはぎ」の残りの黄な粉が冷蔵庫にありました。
初めてなのでちょっとドキドキ…。
一口食べたら、なんだかわらび餅みたい??
娘いわく「黄な粉が一番合うんじゃない!!」だって。
この豆乳ヨーグルト菌を作ってる会社のホームページに、
確かに『和風の素材とよく合います』って書いてありました。
次はこれまたおはぎの残りのあんこで食べてみようかしら…。
【ほし太の日向ぼっこ】
豚骨ラーメン。

娘が福岡の学校に通っていたこともあって、
豚骨ラーメンには馴染み深いです。
ここ茨城県ひたちなか市に、
本場と同じくらい美味しい豚骨ラーメンを出す店があり、
産地に行くと時々寄って食べます。
今回の草取り合宿でも一日目の夕飯にみんなで行って来ました。
写真は「贅沢木耳チャーシュー麺の角」という辛味が足されたもので、
お値段990円。
冷静にみるとけっこう高いですね~。
でも普通の豚骨ラーメンの白は680円だから、
福岡と同じくらいの相場です。
ほかに、餃子1人前と替え玉を半分こ食べたら、
お腹がいっぱいになりました。
当分の間、豚骨ラーメンはいいかな~。
【ほし太の日向ぼっこ】
草取りの楽しみ

過酷な草取り合宿の唯一の楽しみが、
たかおさんのメロン♪
今回はたかおさんのお宅のすぐ裏の畑で作業していたこともあり、
10時に冷えたメロンを持ってきてくれました。
手を洗う水までバケツに用意してくれる気遣いがたかおさんらしいです。
一玉を4等分した贅沢な食べ方は産地ならでは。
それを1人で3切れも食べる豪傑もいます。
ツルから切ってちょうど一週間めのメロンだとききました。
甘くて、ちょうどよい熟し加減で、そのくらいが一番美味しいそうです。
そして夕方には「漬物があるから食べに来い」と、
こんなにたくさんご馳走を用意してくれてありました。
焼きおにぎりに、かぼちゃの煮物、
きゅうりとシロ瓜の漬物(これは生姜醤油につけて)
トマトにゆで卵と、
一日の空腹と疲れが一度に吹き飛びます。
そしてまた次の日の10時にはスイカが届きました。
美味しくて、美味しくて
何より、たかおさんと奥さんの優しさが身に沁みます。
こんなに優しい農家さんと知りあえて
一緒に干し芋作りができるのは、
本当に幸せなことだなあと毎度のことながら、
今回の草取りでも思いました。
【ほし太の日向ぼっこ】
草取り応援

二泊三日で有機のサツマイモ畑の草取り応援に行ってきました。
この草取り、私は心の中で「草取り合宿」と呼んでいます。
なにしろ、一日中ひたすら草取り。
そして寝るのは事務所の床にせんべい布団一枚敷くだけ。
食事も自炊のため、
ご飯を炊いてツナ缶やふりかけ、
よくて野菜と肉を焼いて食べるという過酷なもの。
幸いにも今回は天候が味方となり、
涼しい中で草取りができたことがせめてもの救いかな~?
三日間、写真の畑を5人で草取りしました。
ハクザやスベリヒユがかなり育っていて苦戦しました。

一日終わると体じゅうがあちこち痛くて、
とくに腰は曲がったまましばらく伸びません。
それでも綺麗になった畑を見ると、
達成感で嬉しくなります。
追伸
昨日は「大暑」でした。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「大暑」の直接ページはこちら
大暑
【ほし太の日向ぼっこ】
セミの抜け殻

梅雨明けするとすぐに、例年ならセミが一斉に鳴き始めます。
たしか二年前の今頃、
茨城の草取りから帰ってきたら、
「蛙鳴蝉噪」の季節になっていた…
というブログを書いた記憶があります。
今年は何でセミの声がしないのかな~?
と昨日も友人と話したところです。
ところが今日、庭の木にセミの抜け殻がいくつもついているのを見つけました。
ということはそろそろ蝉噪が聞けるのかな~。
【ほし太の日向ぼっこ】