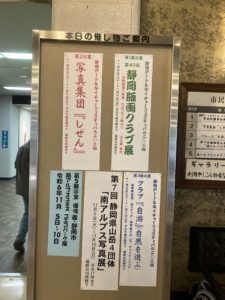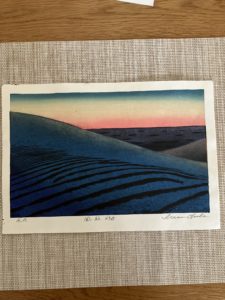11月4日、稲架がけしてあった稲の脱穀にやって来ました。
2日は雨が一日降り、3日は雨があがったものの曇りだったので、
本当に4日に脱穀してもいいのか心配になり、
地元の友人に相談したところ、
「3日夜にシートをかけて4日朝、陽が出る前に外しておきます」
とのこと。ありがたいです。これで夜露は防げます。
それと「充分に陽が当たってから脱穀を始めた方が良いかも」
とアドバイスももらいました。
本来は稲刈から3週間以上は天日に干した方が良いのですが、
仕事が繁忙期になるためこの後のスケジュールを考えると
4日がギリギリのタイミングでした。
稲刈りしたのが10月17日なので実際は19日間の天日干し期間ですが、
前半よく晴れたので乾いていることを信じて脱穀を行います。

4日10時半ごろに田んぼに着くと、
仲間の田んぼもみな稲刈りが終わり、
それぞれの田んぼに稲架ができていました。

毎年のことながら我が家が脱穀一番のりなので、
脱穀機を倉庫から出してきてセットするところから始めます。
だいたいみんなの田んぼの真ん中あたりの田んぼに運び設置しました。
脱穀機の周りをシートとシーツで囲んでセット完了です。

稲架から外した稲を縛っている稲わらを外して、
一握りずつ渡します。
まだ少し雨の影響で湿り気があり、
縛った藁がなかなかほどけませんでした。
こんなことは初めてです。

足踏み脱穀機なので(通称ガーコン)
リズミカルにペダルを踏んで回転する脱穀機に稲を差し込むと、
穂が表面の突起に当たり脱粒します。
それでも籾米の脱粒はなかなか良かったです。

脱穀を始めてから約1時間で終了しました。
友人から借りた大きな箕いっぱいに脱穀した籾と、
稲わらやゴミが混じっています。
このままだと唐箕(とうみ)にかけるのが大変なのでゴミをとり除きます。

籾米を唐箕にかけられるくらいゴミをとり除いたら、
(この作業はやってもやってもキリがないので)
先に脱穀機を片付けます。
周りの布を外してたたみ、シートもどけて角材の台に載せます。

倉庫の中にしまってあった時と同じ状態に、
シートでくるんで、
この後作業する仲間のためにその場に設置したままにしておきます。
【きらくな寝床】