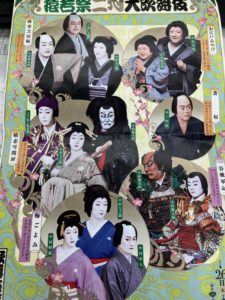腕に三本

朝恒例のランニングの後のシャワーで、
腕に三本のひっかき傷を見つけました。
犯人は愛猫のアシュですが、
この傷がいつできたかの記憶が全くないので、
おそらく眠っている間でしょう。
というのも、
毎晩アシュは私の寝るベットの右側にある
スチール棚の一番上で寝ているからです。
朝までそこにいることもありますが、
夜中に抜け出して走り回ることもあります。
棚は窓とベットの間に挟まっていて、
アシュの寝床の他にはほとんど何もないので、
上から落ちてくるのはアシュだけです(笑)
それも爆弾投下のようにお腹の上だったり、
ひどい時には顔の上に飛び降りてくるので非常に危険です。
落ちてきたら大抵は目が覚めますが昨晩は全く気づきませんでした。