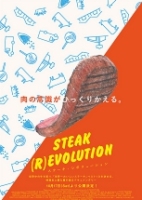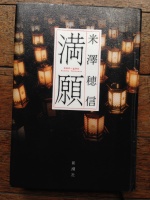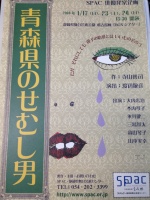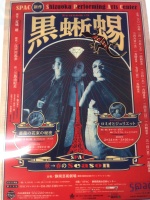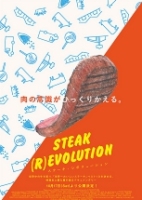
友人のGちゃんから映画のお誘いが…。
それが「ステーキ・レボリューション」との出会いでした。
この映画の存在は全く知らなかったし、
もし知っていたとしてもたぶんみるという選択肢にならなかったと思います。
だからかえって面白そうだなぁと思いました。
地元の上映は静岡東宝会館一館だけ、
上映初日の1月23日夜。
20時10分~の観客は、私とGちゃんと、もう一人だけ。
なんとも贅沢です。
映画の内容はというと、
監督のフランク・リビエラと、
パリでいちばんの精肉店の店主イヴ=マリ・ル=ブルドネックと共に、
2年間の「世界最高のステーキを見つける旅」に出るというもの。
世界20カ国、200を超える有名・無名のステーキ店を食べ歩き、
牧場を訪ねてインタビューするというドキュメンタリーのような映画。
アメリカでエリート達が牛肉の生産者になるという現象や、
スウェーデンで、「和牛」を育てて高額で取引している元物理学者やら、
(その和牛をどうやって輸入したのかも物議を醸しそうですが…)
最近日本でも聞くようになった「アンガス牛」の純潔種を育てているおっかさんやら、
20代のうら若きフランス女性が、ワインの有名産地で牛を育てていたり、
まるで哲学者のような大富豪が、コルシカ島で地産地消の牧場経営をしていたりと、
ランダムなランキング形式で進む、2時間ひたすらお肉と牛の話。
日本の松坂牛も第3位という高位置ながら、
輸入された穀物飼料を与えられ、
まるでドラム缶に短い足がついたような牛の姿を見ると、
疑問を持たずにはいられませんでした。
そして第一位にランキングされたコルシカ島の牛は、
実に健康的にのびのびと育てられていて、
たぶんこれこそが美味しい牛なんだろうなと思いました。
鑑賞後Gちゃんと「どのお肉が食べたい?」と話しました。
いつもは素通りするスーパーの牛肉売り場をまじまじと見て、
「アンガス牛あるじゃん!」と思わぬ発見をしたりと、
私にとってもステーキ革命が起きそうでした。
【ほし太の日向ぼっこ】