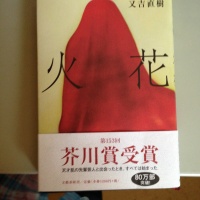沖縄じゅーしぃ
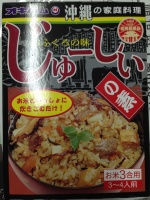
石垣島ツアー三日目は、
朝から青の洞窟ツアーと言うのに参加。
シュノーケリングで泳いで洞窟まで行き探検。
その後シュノーケリングを楽しみ、
(海の上で高所恐怖症になりそうなくらい、
透明度が高く深い海の上を泳ぎました。)
熱帯魚をたくさん見た(ニモが可愛かったです)後、
沢に移動し、滝つぼでターザンごっこ。
クラブハウスに戻りシャワーをあびてホテルまで戻る。
と大変楽しかったのですが、
スマホは持って行けず写真がないため、
地元のJAで買った沖縄風炊き込みご飯の素で作った、
じゅーしぃを紹介します。

お米3合に混ぜて炊くだけ。
仕上げに刻んだニラとごま油を混ぜれば完成!
地元で食べたじゅーしぃが再現できました。
会社のお昼ごはんにしたのでスタッフにも好評でした。