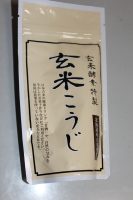きらくな寝床
最後の茗荷

たくさん頂いたので、
毎日、楽しみに美味しく食べていた茗荷がいよいよ残りわずかになりました。
これ以上置いといてもダメになってしまうので、
残りは全部梅酢につけました。
残りといっても27本もあったので、戴いたときはやっぱり100本以上だったことがわかります。
薬味にしたり、刻んだねぎと一緒にみりんと醤油につけたり、
卵とじや、梅酢漬け…と毎日とっても楽しみました。
Gちゃん、本当にごちそう様。

茗荷と一緒に戴いたバジルの葉っぱも、
水に差しておいたら根っこがでてきたけど、
そろそろ使っちゃおうとバジルソースにしてみました。
バジルの葉っぱをむしると70gもありました。
それに、オリーブオイル、にんにく、パルメザンチーズ、塩とミックスナッツ、
隠し味に味噌も入れて、ブレンダーにかけて…
こんな感じになりました。

ちっちゃなビンに2本出来上がったソースは、
色が変わらないうちに冷凍して、
残ったソースはフライドポテトにからめてお弁当のおかずに…。
バジルソースもよくGちゃんに戴いて、
それがとっても美味しいから、今回つくってみたけどちょっと塩分が強めでした。
分量が適当すぎたかな~。
【きらくな寝床】
西部夏祭り

いつも利用させてもらっている『西部生涯学習センターの夏祭り』が、
8月17日18日の二日間あり、
落語愛好会“寝床の会”も18日に参加しました。
おしか座こと“AB亭いまいち”さんによる街頭紙芝居『河童のすもう』から始まり、
”杉山亭花粉”さんによる『小噺とボケの話』。
“磯の家さざえ”による『昔話シリーズとなぞなぞ』
そしてトリを飾ったのが“駒家瓢箪”による『やかん』
後半の合戦場面は圧巻の話しっぷりに思わず会場からも拍手がでました。

毎年評判の手打ち蕎麦2食分600円と、
さくら棒200円をお土産に買って今年の夏祭りも終了♪
【きらくな寝床】
茗荷大好き♪

友人から「茗荷好きですか?」のメール。
「うん大好き!」と返したら、こんなにたくさんくれました♪
お母さんの実家がある新潟へ家族で帰省して、
ミカン箱いっぱいくらいの茗荷を、畑でつんできたそうです。
茗荷って、だいたい4個くらいがパッケージに入っていて100円ぐらいだから、
これって何千円分もありますね。
さっそく薬味にしたり、梅酢につけたり贅沢に頂いてます。
お弁当にも毎日持っていったら、
姪に「茗荷作ってるの?」と聞かれました。

実は茗荷以外にも、ゴーヤもいただきました。
ゴーヤチャンプルーや佃煮、サラダに大活躍します。

ズッキーニと見まごうくらい立派に育ったきゅうりも…。
塩でもんでワカメと酢の物にしました。

で、これが頂いたもの全部。
茗荷の他は、お父さんとお母さんが畑で作った新鮮野菜。
(バジルはベランダのプランターで)
本当にいつも美味しくて助かってます!!
【きらくな寝床】
豆大福風パン

前に友人から歌舞伎座のお土産で、
“歌舞伎座厨房共同企画”のランチパックをもらいました。
求肥と赤えんどう豆入りあんと、
ホイップクリームがサンドしてあってなかなか美味だったので、
スーパーで見つけたときに思わず買ってしまいました。
今回のはさらに豆大福風と書いてある通り、
生地は白いふわふわのパンで、
その生地に塩味の赤えんどう豆が混ぜ込まれ、
求肥とつぶあんとホイップクリームがサンドしてあります。
味は似てるけど、さらに豆大福に近づけたということでしょう。
【きらくな寝床】
カリカリ梅漬け

マメな友人から『青梅のカリカリ漬け』を戴きました。
これを10kg単位で漬けたというのだから、本当にマメです。
塩漬けのも戴いたことがあるけど、これはシロップ漬け。
酸味と甘みがちょうどいい塩梅です。
甘いからお茶請けとして食べていたけど、
昨日カレーのお供に食べたらとってもよく合いました。
だから今日は普通にお弁当にも入れてみたけど、
デザートと漬物の間のような感覚で美味しいです。
どうやって漬けるのか今度聞いてみよっと♪
【きらくな寝床】
自然農の草取り

田植えから三週間たち、
様子を見ながら田んぼの草取りに行ってきました。
事前に町田さんから、「これ以上ないくらいにうまく草が抑えられているかんじ」
と教えてもらっていたので、
是非ともその様子を見たいと楽しみに行きました。
行ってみると、確かにあんなに蔓延っていたクローバーはほとんど目立たず、
スギナが少し出ているくらいでした。
それでも苗代だったあたりと、稲の株周りの草を一通り抜いて、
抜いた草はその場に置いてくるようにしました。
分けつが進んできたので、稲と間違えて植えてしまったヒエがわかるようになり、
ヒエも抜いて、石垣の草も刈り、さっぱりとした田んぼになりました。
共同の場所に植えた黒米の稲周りも草取りし、
時折雨のぱらつく中、順調に作業を終えました。
これであと一か月くらいはもつかな?
【きらくな寝床】
自然農の田植 2013

6月4日に苗床の草取りをしてから約10日、
15日に田植えに行ってきました。
分けつが進んだ苗も多く、たくましく立派に育っていました。

苗床から苗を1本づつ土つきで分けて、
草を刈った田んぼに、苗を植えるところだけ草をよけ、
鎌で少し土を掘って植えていきます。
苗を東南の方向へ向くように、
30センチ×40センチの間隔で丁寧に植えます。

二人がかりで朝の10時から夕方6時過ぎまでやって、
なんとか苗床の手前まで田植えが終わりました(やれやれ)
苗が少し余ったのでみんなの田んぼにも植えてもらいます。
それにしても一番小さな田んぼにしておいてよかった~♪
【きらくな寝床】
自然農苗代の草取り

4月27日に籾まきした苗代。
5月12日の草取りの時はまだ芽が出ず、草もそれほど生えていませんでした。
それから約3週間、2回目の草取りに行ってきました。
心配した苗もどうにか田植えができるくらいまで育っていました。
それに伴って草も勢いを増しています。
サツマイモ畑でも猛威をふるうハクザや、
スギナ、稲そっくり擬態した稗などを抜くと、
稲の苗はまばらになってしまい、
これで田んぼ一面植えられる苗があるだろうかとまたまた心配に…。
とにもかくにも、
いよいよ6月15日から田植えが始まります。

【きらくな寝床】
糀の甘酒
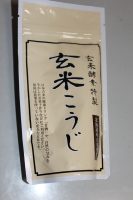
いつも食べている玄米酵素の会社が“玄米こうじ”を試作したものを戴きました。
この糀を使って簡単に甘酒ができるというので、
レシピを参考に作ってみました。
材料は、
玄米こうじ 一袋(100g)
ご飯 160g(茶碗1杯ていど)
ぬるま湯(60cくらい) 300cc
ふたつきの入れ物に、玄米こうじ、ご飯、ぬるま湯を入れてよく混ぜ、
炊飯器に3センチ程度のぬるま湯を張ってから容器ごと入れて
炊飯器の蓋を開けたまま、濡れ布巾をかけた状態で、保温で6時間おく。
というだけの簡単さ。

けれど我が家には電気炊飯器がないので会社から一晩借りてきました。
夜寝る前にセットして朝起きたらもうできあがり。
ご飯と糀を混ぜた直後はほんのり甘いだけで粉っぽかったのが、
朝にはしっかり甘味のある甘酒ができていました。
貴重なので色々料理に使います。
まだ試作品なので販売していないみたいだけど、
売り出したら買いたいな~。
【きらくな寝床】
苗代づくり。

今年はいよいよ個人で一枚づつの棚田を受け持ちます。
そのため棚田の隅に小さな苗代を作りました。
まずは一面に生えている草を苗代を作る部分だけ刈ります。
そして、残った草の根(今回はシロツメクサが多い)を切って取ります。

そして、草花の種をよけるため表面の土を削ってとります。

周りに溝を掘ります。
モグラよけのためと、この時掘った土を後から使います。

表面の土を少し耕して細かくし平にならします。

籾を一粒づつ3センチ四方に置いていきます。

籾の上に細かくした土をかぶせます。
この時、溝から掘り出した土を使います。
両手で細かくしながら籾が隠れるまで根気よくかぶせていきます。

籾が隠れたらまた表面を軽く平にします。

昨年の稲藁を半分に切りかぶせていきます。
最後は切らずにかぶせます。

今年はアナグマが出て、いたずらするそうなので、
最後に不織布をかぶせて完成!!
朝から二人で約5時間。
腰やら肩があちこち痛くなったけど、初めて自分たちだけで作った苗代に達成感いっぱい♪
ここから1週間ほどで芽が出て、2週間後からは草取りです。
【きらくな寝床】