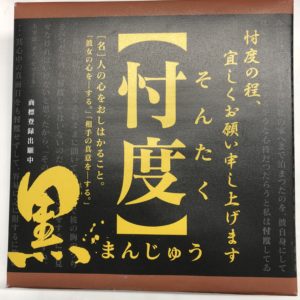キーマカレー

今日は午前中に用事があり、お弁当を作る時間がありません。
そのため前の晩にカレーを作っておきました。
とはいえ、普通のカレーライスはちょっと飽きたので
キーマカレーを作ることにしました。
材料は、
クミンシード、ニンニク、ショウガ、豚の挽肉、
玉ねぎ、人参、セロリ(葉っぱも)、たけのこ、かぼちゃ、ミックスビーンズ。
家にあった使えそうな野菜を、ひたすら細かくみじん切りにしました。
鍋に菜種油をしいてクミンシードを小さじ1くらい入れて炒め、
香りが出たら、ニンニク、しょうがのみじん切りを入れて香りを出します。
玉ねぎ、人参、セロリも入れて炒め、豚の挽肉、タケノコも入れて、
挽肉に火が通ったらカレーパウダーを入れて炒め合わせます。
ここまで行くと野菜からけっこう水分が出てきますが、
水を100cc位入れて、後は味を見ながら調えます。
塩、胡椒、ケチャップ、ソース、味噌、何でも入れます。
ここで、買っておいたカレーの壷という調味料を投入。
これで完成です。
お昼に持って行ったら「作り方を教えて」とスタッフに聞かれました。
使った材料は言えますが分量は全て適当なので、
後は味を見ながら作ってねーと言いました。
そうそう、「カレーの壷」というのは、
第三世界ショップという会社が販売しているペースト状のカレー調味料。
グルテンフリーで、動物性原材料や、化学調味料、保存料も使用していない、
しかもフェアトレードで、
手軽にスリランカカレーが作れるという優れもの。
前になぜかスーパーで見かけて買っておいたのがようやく役に立ちました。
スタッフにも教えましたが、
手に入らない場合はカレールウの辛口を半分くらい入れたらいいんじゃないかな。
煮込む必要がないので、下拵えさえ頑張れば調理は簡単です。