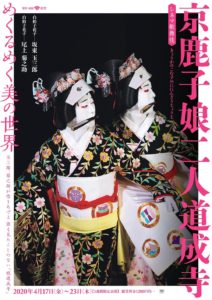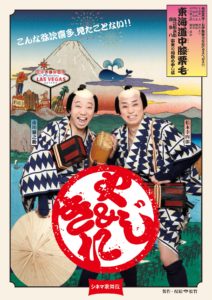ついにやられました(汗)

我が家の飼い猫アシュ君。
トイレは、なぜかツルツルのところがお気に入りで、
普段は洗面台の中で、一生懸命に砂をかく動作をしてから、
おもむろに『大』や『小』をします。
『小』の場合はそのまま水を流せば水洗トイレですが、
『大』の場合はもちろん飼い主の私たちが処理をします。
猫トイレもあるのにほとんど使わないので、
ペットシーツも猫砂も買わなくてすみ経済的ではあります。
困ったことに洗濯機の中もツルツルなのでお気に入りの様子。
むしろ囲われている分、洗面台よりもさらに好ましいらしい。
さすがに洗濯機にされるのは困るので、
中に入れないよう上にスノコを載せています。
しかも最近新しくしたばかりの洗濯機なので、
かなり気をつけていました。
が、今朝は油断しました。
洗濯の量もそんなに多くないので、
干してくるほんの短い間くらいは大丈夫だろうと、
すのこを載せずにほんの5分か10分くらいの時間。
戻ってきたら「何か臭い」。
ついにやられてしまいました。
キレイにしてからアルコールで消毒してと、
余計な手間でした。