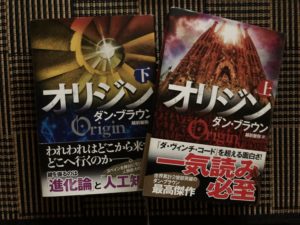ほし太の日向ぼっこ
オリジン ダン・ブラウン
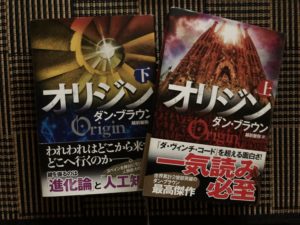
ダヴィンチ・コード以来からのファン、ダン・ブラウンの新作『オリジン』を読みました。
いつものダン・ブラウンの著作に比べて今回は少し薄いのと、
帯には「一気読み必至」と書いてあったので、
すぐに読み終えるだろうとタカをくくっていたら、
時間がかかることかかること…。
われわれはどこから来たのか。
われわれはどこへ行くのか。
今回も人類創生からの謎を追い、
宗教界から進化論、AIも登場し、いつもながら難しい内容ですが、
1、殺人事件 2、その場にいたラングドン教授が巻き込まれ、3、美女と逃亡しながら謎を解く
といういつものパターンで安心しながら楽しんで読めました。
次々と登場する舞台の描写や美術品については、実際のものなので
(今回はガウディの作品群が主でした)、今回もその場所に行きたくなりました。
事件の重要な鍵であるAIの“ウィンストン”については最初からある予感がありましたが、
最後にそれが当たってしまったことが嬉しいような、悲しいような…。
現在の人類に代わり、近い未来生態系の頂点に立つ種というのが、
本当にそうなるかもしれないと思わせられ、
感慨深く読み終えました。
今回も面白かったです。
【ほし太の日向ぼっこ】
追分羊かん

旧清水市(元静岡市)の名物『追分羊かん』を戴きました。
というのも、木版画の仲間が県の版画協会展で、
初出品なのに奨励賞を受賞したことで、
そのお礼にと(私たちは何もしていませんが)
みんなにこの追分羊かんを買って来てくれました。
地元の名物なのでもちろん食べたことはありますが、
そうそう自分で買ってまでは食べません。
ということでとても久しぶりで、嬉しく美味しく戴きました。
追分羊かんは、創業元禄8年とあり、
徳川家光の時代に、明の僧から製法を伝授されたのだとか。
300年変わらず手作業で作られているそうです。
竹の皮に包まれた蒸し羊かんで、
竹の香りがする、甘さ控えめのもちっとした食感です。
かの、ちびまるこちゃんも、
幼いころお小遣いをためて買いに行ったという逸話もあり、
地元ではなじみ深い名物です。
【ほし太の日向ぼっこ】
達磨庵 歳時記の写真

先日の田んぼの共同作業のとき、
電柵にさわっていて泣く泣く刈り取ったコスモスの花を、
そのまま畑の肥やしにするのは勿体無いので家に持って帰って来ました。
2日たっても元気だったので、
ふと10月の歳時記の写真に使えるかも、と思い急遽写真撮りしました。
タイトルはずばり「秋桜」で、
百恵ちゃんが歌った、さだまさしさん作詞の歌詞をイメージしました。
が、事前に準備していなかったので、
中々コスモスと干し芋だけだと難しかったなぁ。
あまりいいできの写真が無かったからもう一度撮りなおしかも。
【ほし太の日向ぼっこ】
お墓参り

秋分の日、主人と二人でお墓参りに行ってきました。
いつもは娘と二人なので土井ファームのランチを食べますが、
そこはパンとジェラートなので、
“おにぎらず”を作ってもって行くことにしました。
具は、スクランブルエッグとランチョンポークときゅうりです。

新清水までは新東名、そこから芝川周りです。
雪のない富士山がうっすら見えました。

お彼岸の中日なので、お墓を訪れる人がとても多かったです。
金木犀の香りがどこからともなく漂ってきて、
早くも紅葉が始まった木もありました。
気温は高めでしたが空気が澄んでいて気持ちよかったです。

無事お墓参りも終わり、
お昼ごはんをどこで食べようかと考えて、
いつも気になっていたお蕎麦の旗が立っているところに行ってみることにしました。
(その前に、おにぎらずは車の中で食べました。
少なめにしたのでお蕎麦なら十分食べられます)
矢印を頼りに行ってみると、
簡易郵便局の母屋の裏にありました。
名前は『そば処 黒門』です。
10人ほどの人が並んでいて、列の最後の方が
「予約していないなら、おそばがあるか聞いたほうがいいですよ」と、
教えてくれました。
聞いてみるとなんと私たち2人でおしまいとのこと。
ラッキーでした。

メニューはシンプルで、
天ぷらそば、天ざる、ざるそば、ざるうどん、おしるこ、のみ。
私たちは天ざるを注文しました。
中では元気のいいおば様方が、天ぷらを揚げる人、おそばをゆでる人、
運ぶ人、店長というように分業されていました。
並び始めてから1時間。
ようやくお目当てのお蕎麦が出て来ました。
てんぷらはサクサクで、おそばに、お豆腐やゴーヤのサラダ、がんもどきの煮物などがつき、
最後はお汁粉までサービスに出して頂きました。
おそばはけっこう大盛りで、おにぎらずを食べてあった分、
かなりお腹がいっぱいになりました。
これで1000円はかなりお安いと思いました。
電話で予約しておけばお蕎麦はとっておいてくれるようなので、
来月は娘を誘ってまた来たいです。
【ほし太の日向ぼっこ】
シシトウの佃煮

先日運転中に聞いていたNHKラジオ“ひるのいこい”。
テーマソングがとっても印象的でのんびりとしたごく短い番組です。
その時、視聴者からのお便りで「この時季はシシトウで佃煮を作っている」と紹介されました。
それを聞いてから一度自分でも作ってみたくて覚えていました。
ちょうどこの前友人のGちゃんから戴いたシシトウがまだ少しあったので、
それを使って作ることにしたのだけれど、
シシトウ味噌を作るのに使ってしまい、量があまりなかったので、
一緒に戴いた細めのピーマンも使うことにしました。
シシトウとピーマンは、半分に切って種を取り出し、
ピーマンはさらに細く切りました。

分量とか調味料の説明はなかったけれど、
「シシトウは湯がいてから…」というのが記憶にあり、
まずはお湯でさっと茹でました。
いつもの私なら、たぶん茹でずにごま油で炒めたことでしょう。
こちらのほうがヘルシーです。
茹でたシシトウとピーマンに、
酒、砂糖、醤油、かつお節1パックをを入れて煮詰めます。

出来上がりました。
カサがけっこう減ってしまったけど、いいご飯のお供になりました。
今日のお昼の一品です。
【ほし太の日向ぼっこ】
懐かしの…

昨晩、漆塗りの同好会でメンバーの一人が持ってきた懐かしの紙袋。
静岡のレコード屋さん「SUMIYA」のLPサイズの紙袋でした。
年季が入っています。

中から出てきたのは、大滝詠一、佐野元春、杉真理のアルバム、
ナイアガラ トライアングルVOl.2 でした。
思わず声が出てしまいました。

こちらがお馴染みの表。
なんと懐かしい。
家にステレオがあれば、すぐに借りて行って聴きたかったところですが、
CDに録音をお願いしました。
次回楽しみです。

ナイアガラ トライアングルは、1982年に発売されたそう。
実際のLPレコードを見たのは始めてかも。

思いがけないところで、思いがけなく懐かしいものに出会うのは感慨深いです。
【ほし太の日向ぼっこ】
木版画

木版画の同好会で去年から作っているカレンダー。
一人が一月担当します。
私は2月担当ですが、新たに作っている時間がないので
製作途中のアシュの版画に無理やりみかんを付け加えて冬っぽくしました。
この前の時間は背景を30枚刷り、
今回は、一部の輪郭とアシュの毛並みの二版を頑張って刷りました。
背景は「つぶし」と言って全面に均等に色をのせなければならないので一番大変です。
今回はアシュの色がついているところの毛並みなので、
わざとムラにのせてみました。
残りは、あと3版。
だんだんと完成が近づいて来ました。
【ほし太の日向ぼっこ】
青蜜柑

私がまだ子供の頃、辺りの山にはみかんの木がたくさん植わっていて、
母親の実家もみかん農家でした。
だから冬になると毎日みかんを食べていました。
今ではみかん山も少なくなり、
母の実家もみかん農家はやめてしまいました。
それでも清水はまだみかん農家が残っていて、
みかん屋さんもあります。
配達スタッフがみかん屋さんで買ってきてくれた青蜜柑。
一山200円だったそうで10個くらいありました。
見た目は酸っぱそうですが甘くて美味しかったです。
今年の初物です。
【ほし太の日向ぼっこ】
リメイク朝ごはん

お昼ごはんにビビンパを作ったとき、
小松菜とモヤシ、ジャガイモをゆでたゆで汁をとっておいて、
簡単コーンスープを作りました。
ゆで汁に野菜ブイヨンとクリームコーン缶を入れ、
塩胡椒で味を調え、とき玉子を流し入れたもの。
それが残ったので、
翌日の朝ごはんにリゾット風にしてみました。
温めたコーンスープに冷ご飯を入れてとろけるチーズをかけて、
旦那様のお味噌汁に入れたカニの身と刻み葱をトッピングしたら完成!
おー意外と美味しい!!
【ほし太の日向ぼっこ】
彼岸花

先日、庭に突然ニョキニョキと茎が生えてきて、
あれよあれよという間に蕾がつき、
今日きれいに開花しました。
彼岸花という名のとおり、毎年お彼岸近くなると出現して花を咲かせます。
父が植えたのでしょうか。
葉っぱがなくて茎の先っちょに花がついているふしぎな花です。
花が終わった後に葉が伸びてくるのだけれど、
花が終わってしまうと彼岸花という印象がなくなり、
どんな葉っぱなのか思い出せません。
別名:曼珠沙華(まんじゅしゃげ)
天上の花という意味らしいですが、私はこっちの呼び方のほうが好きです。
根っこには毒があるため、普段は食せず、
本当に飢饉になった時だけ食べたという話を聞いたことがあります。
【ほし太の日向ぼっこ】