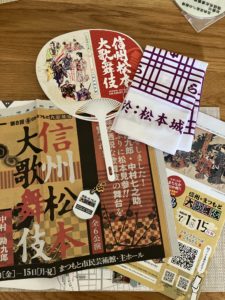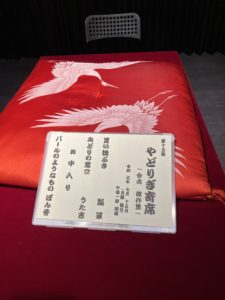納豆こうじ

姪から納豆こうじをもらいました。
知り合いのおにぎり屋さんに作ってもらったのだそう。
以前、友人から納豆こうじ丼というお弁当をご馳走になったことがあり、
納豆こうじが美味しいのは知っていました。
興味がわいて調べたら意外と簡単に作れることがわかりました。
ちょうど家にお味噌づくりで余った麹があったので、
さっそく作ってみることにしました。
ネットのレシピでは、
醤油と酒、各大さじ5を鍋に入れ沸騰したら、
人参1/2本の千切りを入れてさっと混ぜます。
60℃くらいに冷めたら麹100gをほぐして混ぜます。
完全に冷めたら納豆120gを入れてよく混ぜます。
納豆が混ざったら塩昆布25gと白ごま40gを加えてさらに混ぜます。
2~3日熟成させて、麹が柔らかくなったら完成!
冷蔵庫で一か月ほど保存できるそう。
食べるのが楽しみです。