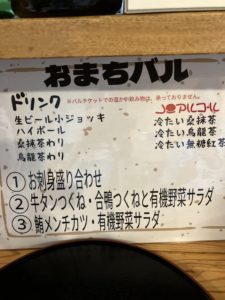6月1日にグランシップで開催された、
広上淳一指揮 NHK交響楽団の演奏会に行ってきました。
今回は、1月に静岡音楽館AOIで聴いた、
上野道明さんの無伴奏チェロ組曲が素晴らしくて、
もう一度上野さんのチェロを聴きたいと思ったからですが、
NHK交響楽団の演奏を生で聴けるのも楽しみでした。
プログラム前半は、
ドヴォルザーク作曲 チェロ協奏曲ロ短調 作品104
ⅠAllegro
ⅡAdagio ma non troppo
ⅢFinale:Allegro moderato
チェロ演奏はもちろん上野道明さん。
70名以上の楽団員で構成された管弦楽の音の洪水に度肝を抜かれ、
その音に負けない上野さんのチェロの音に魅了されました。
広上さんの踊るような指揮にも心を奪われ
まさに天上世界にいるような不思議な体験でした。
休憩を挟んで後半の演奏は、
リムスキー・コルサコフ作曲
交響組曲「シェエラザード」作品35
Ⅰ海とシンドバッドの船
Ⅱカレンダー王子の物語
Ⅲ若い王子と王女
Ⅳバクダッドの祭りー海ー
船は青銅の騎士のある岩で難破ー終曲
バレエ音楽としても有名なこの曲は
バイオリンの演奏がとても印象的でした。
パーカッションも増えて劇的な演出もあり、
また違った音に浸れました。
演奏を聴く前は少し体調がよくなかったのですが、
終わった後はかなり元気が出たので、
いい音楽は免疫力を高めることを実感しました。
アンコール曲は、
ヘンデル作曲「水上の音楽」からアラ・ホーンパイプでした。
ホーンパイプとは17世紀後半に生まれたイギリスのフォークダンス、
又はそのための舞曲とのこと。
この曲の軽快なリズムはステップを踏むためのものだったんですね。
【ほし太の日向ぼっこ】