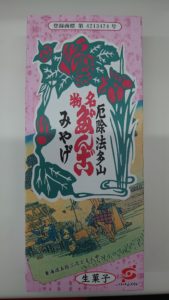干し芋のカツレツ

お昼のお弁当に何を作ろうか迷っていたところに、
真っ白く粉がふいた干し芋が目につきました。
先日事務所で試食した時の余りを冷蔵庫に入れておいて忘れてしまい、
少し固くなってしまったので、
焼いて食べようかと家に持ってきたものでした。
熟成干し芋達磨庵のサイトには干し芋料理のレシピが沢山掲載してあります。
その中で比較的簡単に作れそうなのが干し芋のカツレツだったことを思い出し、
作ってみました。
干し芋の間にチーズをはさみ周りを豚肉の薄切りで包んで衣をつけて揚げました。
今日はちょうど黒はんぺんのフライも作る予定だったので丁度良かったです。

初めて食べましたが干し芋のカツレツはなかなか美味しかったです。
とはいえ黒はんぺんのフライでパン粉を使ってしまいほぼ天ぷら。
食べたスタッフ全員からは高評価をもらいました。
ただ干し芋味が強くて間にはさんだチーズや豚肉の味はあまりわからなくて、
ちょっと固いサツマイモコロッケのような感じでした。
他のおかずは、長ネギと油揚げの炒め合わせ、かぼちゃの含め煮、
切り干し大根とワカメ、小松菜とハムの中華風サラダでした。
毎日のメニューを考えるのも一苦労です。