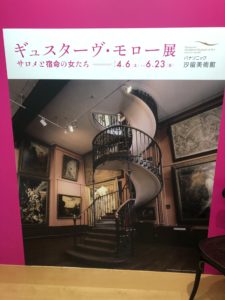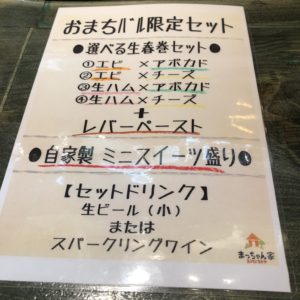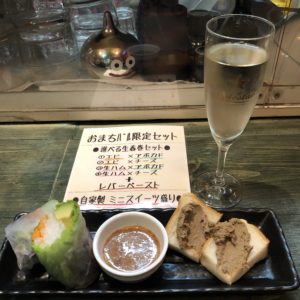自然農の田んぼ 2019 『共同作業と田植え』

6月2日、共同作業の草取りと、
自分たちの田んぼの田植えに行ってきました。
一足先に田植えが終わった隣の慣行栽培の田んぼには、
鴨や鷺やカラスが来ていました。
のどかないい風景です。

共同作業は、田んぼの周りを囲っている柵周辺の草取り。
猪や鹿対策にこの春、電気の柵からこの柵に変えました。
電柵よりも手入れは楽ですが、それでも草がぼうぼうになっては困ります。
また巻きつくところができたためか、つる草が増えた気がします。

次に共同の苗床の草取り。
ここには赤米と黒米の苗が植わっています。
モグラに2回入られてしまったそうで、
真ん中のところは苗がなくなっていましたが育ちはいいです。
人数がいるので草取りもすぐに終わりました。

共同作業が終わり、お昼までまだ時間があったので、
そのまま自分たちの田植えに突入。
先週刈っておいた草がちょうどいい具合に枯れていました。

まずは苗とり。
先に苗の根を痛めないように土を湿らせます。
先週苗床の草取りもしたので、草は殆どはえていません。
一週間で苗もぐんと伸び、おかげで苗とりはかなり楽でした。

1/3ほど苗を採ったら田んぼに植えていきます。
今年は苗の本数が少ないので、株間も条間も45cmにしました。
昨年は30cm×30cmだったのでかなり広々していますが、
仲間に聞くと45cm間隔はけっこうやっていたそうです。

草をどけて苗を植える場所を鎌で掘り、苗を置いてから、
土をやさしくかぶせて回りを抑えてから周囲に草をかぶせます。

一列に15本から16本植えていき、
心配だった苗の本数は、
少し足りないくらいでなんとか田んぼ全体に植え終わりました。

最後は苗床も平らにならし、
周囲の溝も掘りなおし水を引き入れると、
しばらくして田んぼ全体に水が回りました。

田植えは自然農の米作りの中で、一番大変な作業です。
腕と肩と腰は悲鳴をあげていますが、
何とか無事に終わり、ほっとしました。